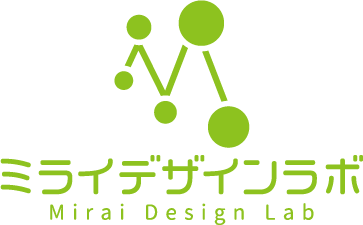なぜ中学生は勉強が嫌いなのか
〜「やる気がない」の奥にある本当の声〜
中学生と日々接していると、必ずといっていいほど耳にする言葉があります。
「勉強なんてつまらない」「どうせやっても無駄」「やる気が出ない」
私たちミライデザインラボでは、この“勉強嫌い”の背景にある本音を丁寧に掘り起こすことを大切にしています。ただ「サボっている」「甘えている」と見るのではなく、その子の“心の声”に耳を傾けることで、驚くほど前向きに変わっていく姿を見ることがあるからです。
勉強が「嫌い」な理由は、本当に一つじゃない
勉強が嫌い、という言葉の奥には、実にさまざまな感情や背景があります。いくつか代表的な例を挙げてみましょう。
1. わからないからつまらない
これは最も多いパターンです。学年が上がるにつれて授業のスピードも速くなり、少しつまずくとどんどん置いていかれる感覚になります。理解できないから授業がつまらない。つまらないから集中できない。結果として成績が下がり、さらにやる気を失う――そんな悪循環にはまっている子は少なくありません。
2. 勉強の意味が見えない
「なんでこんなこと勉強しなきゃいけないの?」という声もよく聞きます。大人から見れば「将来のため」「高校受験のため」と思うかもしれませんが、中学生にはピンと来ないことがほとんどです。特に、自分の将来像がまだぼんやりしている子にとっては、“今の努力”と“将来の報酬”が結びつかないのです。
3. 比較されることへの疲れ
「お兄ちゃんはもっとできたのに」「○○さんは頭がいいのに」――こうした言葉が知らず知らずのうちに、子どもを追い詰めていることもあります。自己肯定感が下がり、自分なんてどうせ無理、と感じてしまえば、勉強そのものに向かう気力も湧かなくなります。
4. 「失敗したくない」から逃げてしまう
意外かもしれませんが、完璧主義の子ほど「勉強嫌い」になりやすい傾向があります。「やったのにできなかったら恥ずかしい」「どうせ頑張っても100点じゃなかったら意味がない」と思い、最初からチャレンジしない――これは失敗を極度に恐れる心の防衛反応です。
コーチング的アプローチで見える「可能性」
では、こうした「勉強嫌い」な中学生たちに、私たちはどう関わっていけばよいのでしょうか。コーチングの視点から言えることは、「その子の声を聴き、問いかけを通じて内側から“やる気”を引き出すこと」が大切だということです。
コーチングでは、「答えはその人の中にある」と考えます。勉強をやりたくない理由、そして本当はどうなりたいのか。そういった問いを一緒に探っていくことで、子どもたちは少しずつ「自分の人生を自分で選ぶ」感覚を取り戻していきます。
たとえば、「どうして勉強って嫌いなの?」という問いを投げたときに、「だって英語が全然わからないんだもん」と返ってきたとします。ここで「じゃあ、毎日10分だけ一緒に英語やってみる?」というように、共に一歩を踏み出す提案をするのです。
「やらされる勉強」ではなく、「自分で選ぶ勉強」へ。
それを可能にするのが、ミライデザインラボのコーチング型アプローチです。
子どもたちは「自分を信じていい」と知りたがっている
最終的に私たちが目指したいのは、成績の向上だけではありません。子どもたちが「自分はやればできる」「自分の未来には価値がある」と信じられること。勉強ができるようになることも大切ですが、それ以上に「自分の可能性を信じる心」を育むことが、未来をデザインするための土台になります。
中学生の「勉強が嫌い」は、心のSOSでもあります。私たち大人が、子どもたちのつまずきにもっと優しく、丁寧に寄り添えたとき、彼らはまた、前を向いて歩き始めるはずです。
ただし、コーチングにも限界があります
ここまでコーチングの有効性をお伝えしてきましたが、最後に一点、誠実にお伝えしたいことがあります。
コーチングは、そもそも「目標に向かって進もうとしている人を支援する」ための枠組みです。そのため、勉強そのものに目標を持っていない子どもや、勉強とはまったく別の方向に関心がある子に対して、「勉強するモチベーションを引き出す」ことは、どうしても難しい場面があります。
そういうときこそ、コーチングだけに頼らず、環境づくりや成功体験、信頼関係の構築など、もっと広い視点で子どもに寄り添うことが必要だと、私たちは考えています。
大切なのは、「勉強させること」よりも、「その子が自分の人生を信じられること」。
ミライデザインラボは、そんな学びと成長の場でありたいと願っています。