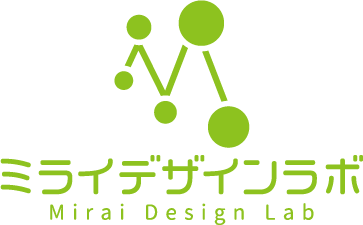中学生の勉強とSNSルールの作り方
こんにちは。ミライデザインラボのブログへようこそ。
今日は「中学生とスマホの関係」について、お父さんお母さんと一緒に考えてみたいと思います。
スマホは学力にどう影響するのか?
まず、はっきりさせておきたいのは、スマホの使用が学力に悪影響を及ぼすということです。
たとえば東北大学の研究では、1日の家庭学習時間が長くても、スマホの使用時間が多ければ、学習効果が著しく低下するという結果が出ています。
つまり、「勉強してるけどスマホも長く使ってる」では、意味が薄れてしまうのです。
これは集中力や記憶力が分断されるから。脳がマルチタスクに対応できないことは、脳科学でも明らかにされています。
世界のトップ経営者たちは子どもにスマホを与えなかった
アップルの創業者スティーブ・ジョブズは、自分の子どもにはiPadもスマホも使わせなかったそうです。
ビル・ゲイツも、子どもが14歳になるまではスマホを持たせなかったと公言しています。
自分たちが開発したテクノロジーの「中毒性」をよく理解していたからこその判断でしょう。
お父さんお母さんにお願いです。
「周りの子が持っているから」ではなく、わが子の将来にとって本当に必要かどうかを考えてみてください。
SNSによる人間関係トラブルも
学力への影響だけではありません。
LINEなどのSNSを通じたやりとりで、子どもたちの間にトラブルが起こるケースも増えています。
スタンプを返さなかった、既読スルーした、誰をグループに入れるか…。
大人からすれば些細なことでも、思春期の子どもにとっては大きなストレスになるのです。
スマホは子どもたちの心の中にも静かに影響を及ぼしています。
でも、スマホは今や“必需品”
とはいえ、現実問題として、中学生にとってスマホは今や連絡手段、情報収集、娯楽などあらゆる役割を担う“必需品”にもなっています。
完全に排除するのはむずかしい。
だからこそ必要なのが、「ルールをつくる」ことです。
スマホルールは“親が一方的に決めない”
スマホルールを決めるとき、ついやってしまいがちなのが「親がルールを決め、子どもに守らせる」という形です。
でも、このやり方では、反発やごまかし、隠れての使用につながることもあります。
特に思春期は、「自分で決めたい」「納得したい」という気持ちが強い時期。
だから、ルールは親子で話し合って、一緒に決めることがとても大切なのです。
話し合いの鍵は「問いかけ」
では、どのように話し合えばいいのでしょうか。
おすすめは、「問いかけ」の形で進めることです。
- 「スマホって、どんなときに一番使ってる?」
- 「使いすぎると、どんなことが起こると思う?」
- 「宿題とスマホ、うまく両立するにはどうしたらいいかな?」
- 「夜は何時までだったら使ってもいいと思う?」
こうした対話を通じて、子どもが自分で考える場をつくることが大切です。
自分で考えたルールは、自分で守りやすくなります。
合意したら「書面化」して共有する
話し合って決めたルールは、できれば紙に書いて見える化しましょう。
「スマホ利用の約束カード」や「家庭内スマホ契約書」など、少し大げさでも構いません。
家族の目につくところに貼っておくのもおすすめです。
たとえば、こんな内容が考えられます。
- 平日は夜21時までしか使わない
- 食事中はスマホを見ない
- SNSでのやりとりにトラブルがあれば親に相談
- 宿題が終わってから動画を見る
- 使いすぎた日は翌日休む、など
ルール違反が起きたときは「粛々と対応する」
ここで一番大切なのは、「違反時の対応」です。
お父さんお母さんにお願いです。
ルールを破ったときには、「じゃあ、ルールだからこうするね」と感情を交えず、淡々と対応してください。
これは罰ではありません。
自分の行動がもたらした“当然の結果”として、ルールが適用されるだけなのです。
叱る必要はありませんし、怒る必要もありません。
親が感情的にならずに対応することで、子どもは「ルールには意味がある」と理解していきます。
自律の力を育てるには
もちろん、最初から完璧に守れる子ばかりではありません。
ときには忘れたり、つい流されたりすることもあるでしょう。
そんなときには、「守れなかったね。でも次はどうする?」と、未来に目を向けた対話を心がけてください。
ルールは子どもを縛るものではなく、**自分をコントロールする力を育てるための“道しるべ”**です。
親は、その道しるべをともにつくり、支える役割を担っていくのだと思います。
最後に:スマホと共存する力を育てよう
スマホはこの先、子どもたちの人生にずっとついてまわる道具です。
だからこそ、「持たせない」のではなく、「どう使うか」を一緒に考えることが何より大切です。
スマホに使われるのではなく、スマホを使いこなす力を育てていきましょう。
それが、学力だけでなく、生きる力を育てる一歩になると僕は思います。