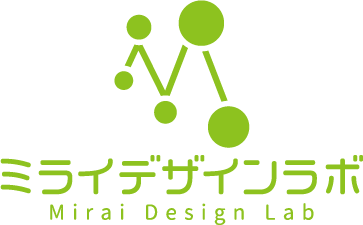日曜日の朝。 ソファでスマホを眺めているお子様の姿を見て、心の中でザワザワとした不安が広がっていく…。
「来週から、またテスト範囲が進むのに…」
「中間テストの結果、あまり良くなかったじゃない…」
そして、つい口から出てしまう、あの一言。
「ちょっと、いつまでスマホ見てるの! 勉強しなさい!」
安城市の自立学習型コーチング塾「ミライデザインラボ」です。
お子様の将来を思うからこその、愛情のこもった一言。そのお気持ち、痛いほど分かります。
しかし、もしお子様の本当のやる気を引き出したいと願うなら、その「勉強しなさい」という言葉は、今日から封印しなくてはならないかもしれません。 なぜならその一言は、脳科学的に見ても、子どものやる気を奪ってしまう、最も効果的な言葉の一つだからです。
■ なぜ、「勉強しなさい」は逆効果なのか?3つの理由
良かれと思って言った言葉が、なぜ逆効果になってしまうのでしょうか。そこには、子どもの心の中で働く、3つのメカニズムが関係しています。
1. 心のシャッターが下りる「心理的リアクタンス」
人は、他人から行動を強制されたり、自由を奪われたと感じたりすると、無意識にそれに反発し、逆の行動を取りたくなる心理が働きます。これを「心理的リアクタンス」と言います。 「勉強しなさい」と言われた瞬間、お子様の心の中では、「今やろうと思ってたのに!」「言われたから、やりたくなくなった!」という反発心が芽生え、固くシャッターが下りてしまうのです。
2. 「自分からやろう」という主体性を奪ってしまう
もしかしたらお子様は、「あと5分、この動画を見たら勉強を始めよう」と考えていたかもしれません。 しかし、その前に親から言われてしまうと、その行動は「親に言われたから、仕方なくやること」に変わってしまいます。自ら行動しようとしていた貴重な「主体性の芽」を、親の言葉が摘み取ってしまっているのです。
3. 「あなたのことを信用していません」というメッセージに聞こえる
「勉強しなさい」という言葉の裏には、「どうせあなたは自分からやらないでしょ」「私が管理しないと、あなたはダメなのよ」という、不信のメッセージがお子様には聞こえています。 信頼されていないと感じながら、前向きなエネルギーが湧いてくる人はいません。この言葉の繰り返しは、自己肯定感を下げ、親子関係にまで溝を作ってしまう危険性があります。
■ では、どうすれば? コーチングが導く「魔法の質問」
では、「勉強しなさい」の代わりに、どのような言葉をかければ良いのでしょうか。 その答えが、私たちミライデザインラボが最も大切にしている「コーチング」の考え方の中にあります。
それは、「命令」を「質問」に変えることです。 お子様を「管理する対象」として見るのではなく、「一人の人間として、その子の目標を応援するサポーター」に、親の役割を変えるのです。
もし、お子様が勉強に向かわず、ダラダラしているように見えたら、一度ぐっとこらえて、こんな**“魔法の質問”**を投げかけてみてください。
「次の期末テスト、あなたにとって、どうなったら最高かな?」
この質問には、お子様の心のシャッターを開ける、いくつかの仕掛けがあります。
- 「命令」ではないので、反発心が生まれない。
- 「あなたにとって」と、主語がお子様自身になっているため、自分のこととして考え始める。
- 「どうなったら最高かな?」と、未来のポジティブな結果に意識を向けさせる。
もちろん、すぐに「よーし、勉強するぞ!」とはならないかもしれません。 「そりゃ、良い点取れたら最高だけど…」と、面倒くさそうに答えるだけかもしれません。 しかし、重要なのは、そこから対話が始まることです。
「良い点か。例えば、苦手な数学で80点取れたら、最高じゃない?」 「そうだね。そのために、何かできそうなことってあるかな?」 「何か、お父さん(お母さん)に手伝ってほしいこと、ある?」
このように、質問を重ね、お子様自身の口から「じゃあ、少しやってみるか」という言葉を引き出す。 これが、本当の意味で「やる気」に火をつける、コーチング的アプローチです。
■ お子様の、一番のコーチになるために
「勉強しなさい!」という命令は、短期的にはお子様を机に向かわせるかもしれません。 しかし、「どうなったら最高かな?」という質問は、お子様が自らの意志で未来について考え、行動するきっかけを与えます。
このコーチングに基づいたコミュニケーションは、一朝一夕にできるものではなく、少し練習が必要かもしれません。 ミライデザインラボは、生徒のやる気を引き出すプロであると同時に、保護者の皆様にとっても、お子様との関わり方について一緒に考えるパートナーでありたいと思っています。
もし、お子様への声かけに悩んでいたら、ぜひ一度、無料学習相談にお越しください。 私たちは、お子様の成績を上げるだけでなく、ご家庭での対話がより良いものになるためのお手伝いもさせていただきます。