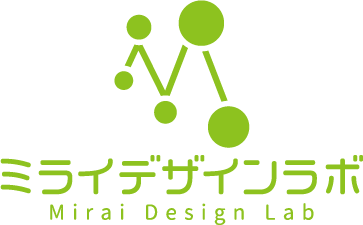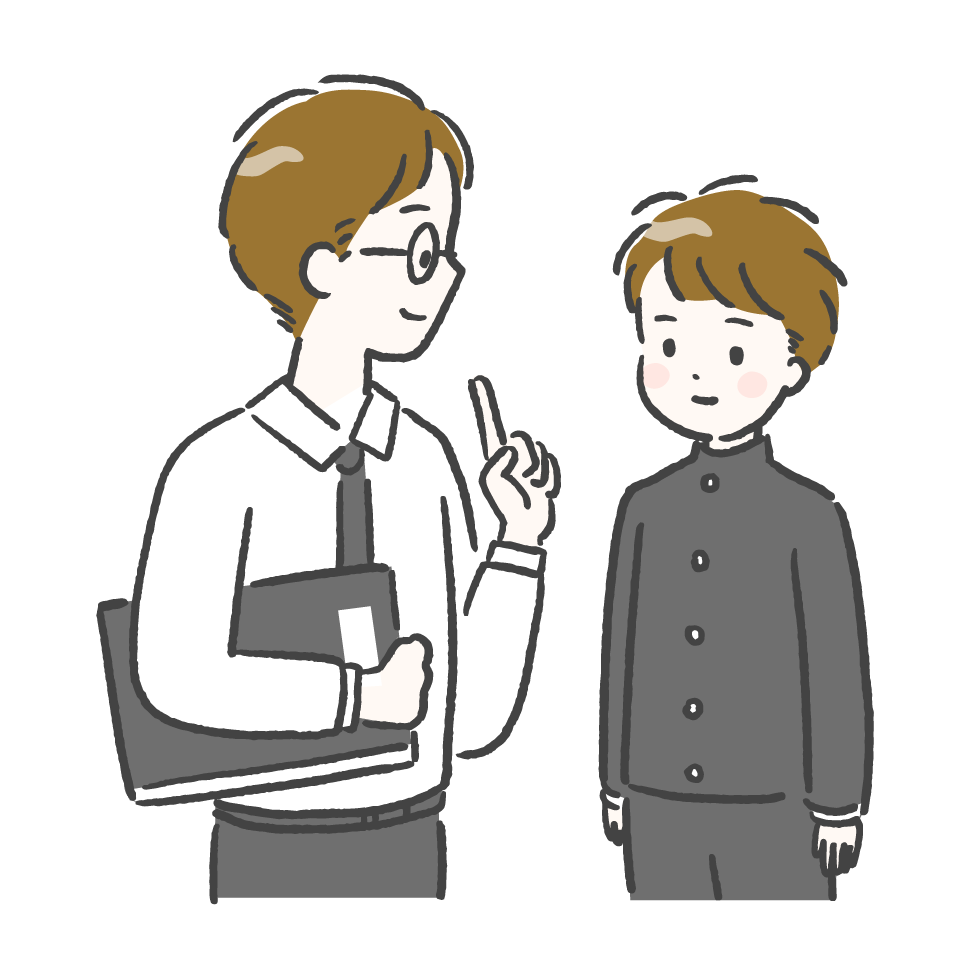ここに書かれていることが常に正しいとは限りません。
大事な情報探しは一次情報を探し手に入れるところから始めて下さい。
必ず愛知県のウェブサイトから最新の情報を調べましょう。
「愛知県の公立高校入試って、内申点と当日点、結局どっちが大事なの?」
これは、すべての受験生と保護者の皆様が抱く、最も大きな疑問です。
この問いに正確に答えるには、巷の噂や前年度までのイメージではなく、愛知県教育委員会が公表している**「入学者選抜実施要項」に定められた公式ルール**を正しく理解することが不可欠です。
今回は、この公式ルールに記載されている事実にのみ基づいて、合否を分ける重要な仕組みを、順を追って分かりやすく解説します。
まず、合否の基礎となる「2つの得点」を知ろう
一般選抜では、まず受験生一人ひとりの「評定得点」と「学力検査合計得点」という、2種類の持ち点が確定します。
入試要項によると、それぞれの得点は以下のように定められています。
- 評定得点(内申点)調査書に記載される、中学3年生の9教科の成績(5段階)の合計(最高45点)を2倍した、最高90点満点の点数です。
- 学力検査合計得点(当日点)国語、社会、数学、理科、英語の学力検査5教科の合計点です。各教科22点満点で、合計点は最高110点満点となります。
(※一部の専門学科では、特定の教科の配点を高くする「傾斜配点」が行われます)
次に、高校からのメッセージ「5つの計算式」を理解する
次に、上で算出された2つの得点を、各高校が選択した計算式に当てはめて、合否の基礎となる数値を算出します。
この計算式こそが**「校内順位の決定方式Ⅰ〜Ⅴ」です。どの計算式を選ぶかは、その高校が「内申点を頑張ってきた生徒」と「入試本番に強い生徒」のどちらをより高く評価したいか**、というメッセージそのものです。
| 方式 | 計算式 | 特徴(高校からのメッセージ) |
| 方式Ⅰ | (評定得点) + (学力検査合計得点) | バランス型:内申点と当日点を平等に評価します。 |
| 方式Ⅱ | {(評定得点) × 1.5} + (学力検査合計得点) | 内申点重視型:内申点を1.5倍し、中学での日々の努力をより高く評価します。 |
| 方式Ⅲ | (評定得点) + {(学力検査合計得点) × 1.5} | 当日点重視型:当日点を1.5倍し、入試本番での得点力をより高く評価します。 |
| 方式Ⅳ | {(評定得点) × 2} + (学力検査合計得点) | 超・内申点重視型:内申点を2倍。中学での成績が極めて重要になります。 |
| 方式Ⅴ | (評定得点) + {(学力検査合計得点) × 2} | 超・当日点重視型:当日点を2倍。入試本番での高得点が強く求められます。 |
まずは、ご自身の志望校がどの方式を採用しているのかを知ることが、受験戦略の第一歩となります。(※各校が採用する方式は、要項の「別記8」に一覧で記載されています)
最終判断のルール:「総合的に行う」とは?
上記の計算式で算出された数値は、あくまで**「基礎資料」として扱われます。
入試要項では、この基礎資料とした上で、最終的な校内順位は、
「調査書情報」「学力検査の成績」「面接等の結果」といった全ての資料とあわせて「総合的に行う」**と定められています。
【補足】ボーダーライン上では、何が考慮される可能性があるのか?
では、この「総合的に行う」という規定は、特に合格ライン上で複数の受験生が僅差で並んだ場合に、どのように影響するのでしょうか。
ここからは、要項の文言が示唆する可能性についての補足です。
点数化された「基礎資料」だけでは甲乙つけがたい場合、要項に定められた他の資料、つまり調査書に記載された**「特別活動の記録」や「総合所見」、面接での受け答え**といった、
数値化されていない要素が評価の対象となる可能性を示唆しています。
ただし、その評価がどのような基準で行われるかは公開されていません。
したがって、私たち受験生にできることは、
- 志望校の計算式を意識し、1点でも多く「基礎資料」の得点を積み上げること。
- そして、もしもの僅差の勝負に備え、日々の学校生活に真摯に取り組むこと。
この二つに尽きます。
まとめ
愛知県の公立高校入試は、自分の強みと志望校の方針を理解し、戦略を立てることが非常に重要です。
- まず、志望校の「方式」を知り、目標点を設定する。
- 次に、その目標に向かって学習計画を立て、実行する。
- 同時に、中学校での活動や生活態度も大切にする。
入学試験において信じていいのは、募集要項や選抜実施要項といった、オフィシャルに発表されている内容だけです。これをどう読み取って、どう解釈するかは、まぁ読み手の自由ではありますが邪推し過ぎて足下をすくわれないようにして欲しいと思います。
世の中には都市伝説的に語られている、理解不能な話もいっぱいありますから、そういうよくわからない根拠不明の話におどらされないようにしましょう。
数値化されていない通知表の記載内容がどれほど素晴らしいことが書いてあったとしても、何十点もの得点差を乗り越えて大逆転合格なんてことはたぶんないと思います。
なんでかって。
そういうよくわからない根拠で大幅に得点をつけられるなんて合否があまりに不安定ですし、説明責任を果たせるとは到底思えないからです。入試は厳格に行われるものですから、不正が疑われるような設計にすることは難しいだろうと考えます。
まぁそういうめんどくさいことにエネルギー注ぐよりは、最初っからボーダー上にのらないぐらい圧倒的な合格を目指して欲しいものです。
ミライデザインラボでは、この公式ルールを基に、一人ひとりに合わせた最適な学習戦略を、コーチングを通じて一緒に考えていきます。ご不安な点があれば、いつでもご相談ください。